 健康
健康 グループで運動すると幸福度が上がる?心理学が明らかにする驚きの効果
私たちの多くは「運動=筋肉を鍛える」「体を健康に保つ」というイメージを持っています。しかし近年の心理学や健康科学の研究では、それだけではなく「幸福度」に大きな影響を与えることがわかってきました。特に注目されているのが グループでの運動 で...
 健康
健康  健康
健康  ギャンブル
ギャンブル  健康
健康  健康
健康  健康
健康  健康
健康  健康
健康 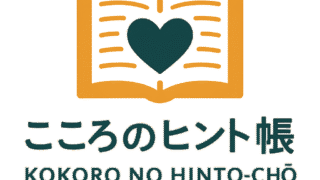 健康
健康 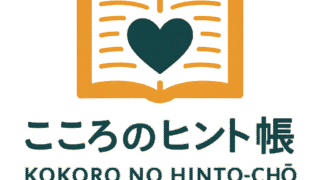 健康
健康