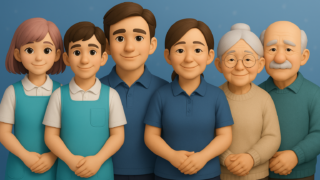 介護知識
介護知識 臥床(がしょう)とは?まず言葉をそろえよう
安静臥床(がしょう)の種類と目的を、介護現場でわかりやすく解説。安静臥床・習慣性臥床・終末期の臥床の違い、体位交換や除圧、口腔ケア、便秘・脱水の観察ポイント、声掛けのコツまでまとめました。
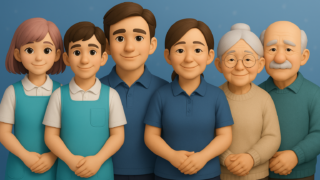 介護知識
介護知識 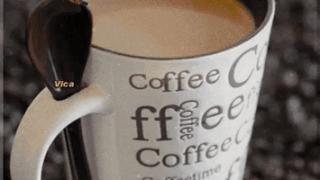 アセスメント
アセスメント 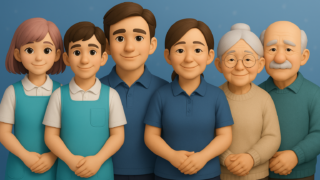 私の介護履歴
私の介護履歴 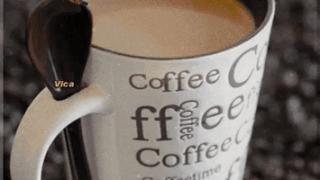 私の介護履歴
私の介護履歴 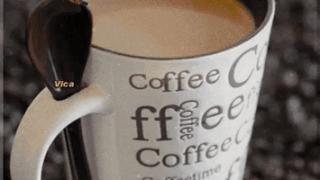 私の介護履歴
私の介護履歴 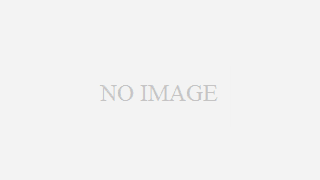 Uncategorized
Uncategorized